アイオワ州建築見学(デモイン・アートセンター/パパジョン彫刻公園/クラウス・ゲートウェイ・センター)
デモイン・アートセンター
5月4日と5月8日の2回にわたってデモイン・アートセンターを訪問しました。一度目の見学では主に建築の内部を、2度目の見学では主に周辺の庭園と建築の概観を見学しました。 デモイン・アートセンターはエリエル・サーリネン(1837-1950)、IMペイ(1917-2019)、リチャード・マイヤー(1934-)の三人の建築家によって建てられた建物です。サーリネンによる最初の建築が1948年に竣工したのち、1968年にはペイの建築が、1985年にはマイヤーの建築が増築され、現在の姿となりました。作品展示部分の導線は建築の竣工順となっており、大きく異なる3つの建築とそこに展示された作品とのコラボレーションが魅力的です。
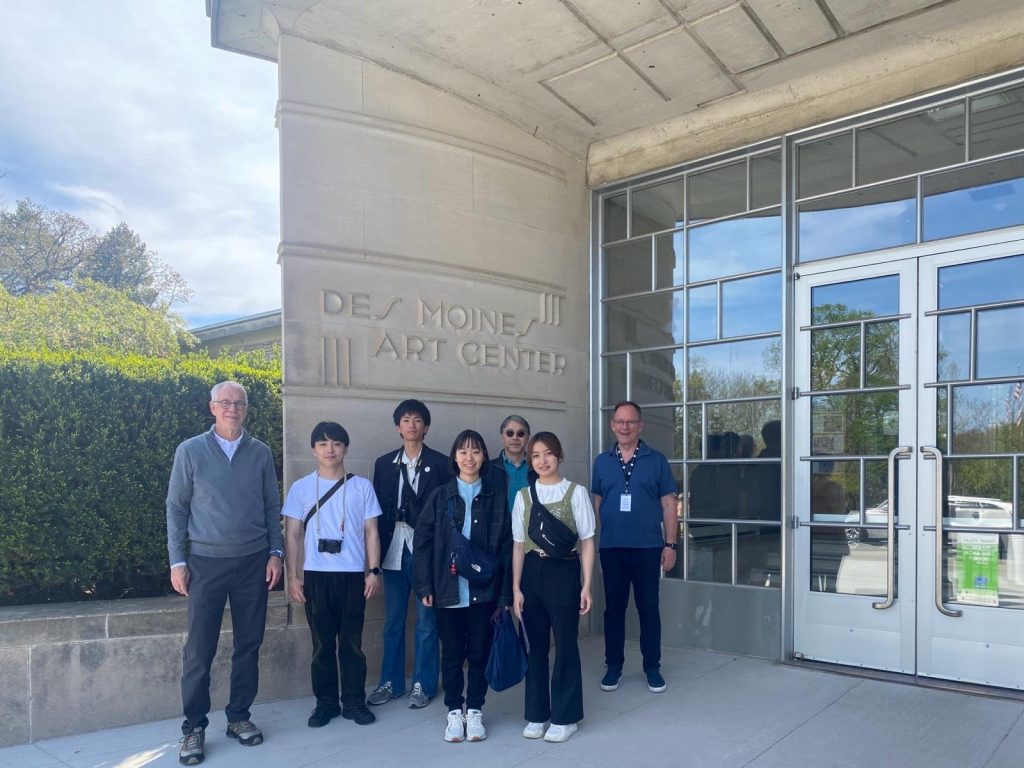
サーリネン館
サーリネン館の石積みの外壁は、使われている石の大きさがひとつひとつ異なります。水平に長細い石材が用いられ建物の水平性を強調している一方で、その積み方に規則性はなく、壁面から少し飛び出ている石もあります。石の質感と飛び出した石材の凹凸によってつくられる軽やかな陰影が非常に美しかったです。
館内では、特に照明計画が特徴的です。照明器具は天井の中に隠され、光源が直接見えないよう設計されており、柔らかい光が館内全体に広がっています。建築の一部はIMペイによって修繕されており、サーリネンによる空間とペイの空間を視覚的に区別できるよう通路の壁面に意匠が施されていました。



ペイ館
ペイ館の特徴である無骨で力強いコンクリートの壁面は、その素材感が前面に押し出されており、迫力があります。一方で、天井から柔らかく差し込む自然光が、空間全体に落ち着きを与えていました。特に南側の壁面は、光をそのまま取り込むのではなく、過剰に入りすぎないように設計された断面構成になっており、光の質がコントロールされています。空調設備も空間に溶け込むように計画されており、空調がどこにあるのか探すのも楽しかったです。足元に目を向けると、石材の床面には、ところどころに金色の要素が散りばめられており、光を受けてさりげなくきらめく様子が非常に印象に残っています。
よく見ると、コンクリートの壁に開けられた小さな穴に、作品展示用の金具(ドライバーのようなパーツ)が差し込まれていて、壁そのものが展示装置として機能しているのも特徴的です。
ペイ館は、細部にまで行き届いた繊細な設計と、大きな折板屋根に天井開口が設けられた大胆な形態の対比が魅力的な建物でした。そこに展示されているのは、立体的な絵画や大判の壁面作品、彫刻作品など、スケール感のある作品群で、建築と作品が影響し合う豊かな展示空間でした。
マイヤー館
マイヤー館は白い壁に多くの開口を設けた開放的な空間が特徴的な建物です。全体は9つのブロックに分かれており、それぞれの部屋で少しづつ雰囲気が変わっていきます。特に天井はなめらかな曲線だったりHPシェルのような造形だったりと大きく印象が変わっていました。
個人的に最も印象的だったのは営繕の方法で、特に窓ガラスは色が違っていたので意匠の一部なのかと質問したところ、改修時に違う色の窓ガラスを使ってしまったのではないかと教えていただきました。壊れたところはいったん直してみてその方法が間違っていたらまた直してみる、というとりあえずやってみるところが日本と大きく違うと感じた次第です。

パパジョン彫刻公園/クラウス・ゲートウェイ・センター
パパジョン彫刻公園は彫刻作品が常設されている公園で、デモイン・アート・センターとデモイン市が共同で管理しています。市内の中心部にあり、周辺には飲食店や雑貨店のほか、図書館などもありました。公園は全面芝生で、放物線状の丘がところどころに形成されています。公園に来ていた子供たちは彫刻で遊んだり、芝生で寝転がったりしながら過ごしていました。
遊びと芸術が共存しているこの公園は、島根県立美術館前の岸公園と似ています。一方で、市街地の中に突如として現れるパパジョン公園は、岸公園よりもより住民に開かれているように見えました。都市の中における美術館の役割や、日常生活における芸術との接点、彫刻という芸術の形式が持つ開放性について考えさせられました。


レンゾ・ピアノ(1937-)によって設計されたクラウス・ゲートウェイ・センターはパパジョン公園の目の前にあります。建物全体は細い柱によって支えられており、その柱も床面のグリッドの頂点に合わせるように配置されています。全面ガラスの開放性の高い建物である一方で、階ごとに深さの異なる庇が伸びることによって室内には直射日光は入りにくく、内部空間は落ち着いた雰囲気を持っていました。
建物の庭部分には音に関連する作品がいくつか設置されていました。日本においては公共性を高めることができる要素の一つとして水辺が用いられることが多い印象ですが、アイオワでは彫刻や音の出るアート作品など芸術が公共性を高める要素として機能していた点が非常に印象的でした。


おわりに
私にとって初めての海外となりましたが、温かく迎えてくださった中村先生、ロブ、ホストファミリーのエマ、ノーラン、そしてチームメンバーと学生の皆さんのおかげで楽しく学びのある10日間を過ごすことができました。
今まで日本であまり活動していない建築家の作品は写真や文章で見ることしかできなかったのですが、実際の建物に触れることで、建築のもつ雰囲気や自分の思い描いていた作品像とは大きく違っていたことに衝撃を受けました。
また、アメリカでの生活は大学での活動から食事、お風呂や洗濯に至るまですべてが新鮮で興味深かったです。
最後になりましたが、貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございました。この場を借りて深く感謝申し上げます。
修士1年 庄野那奈


